研究紀要
| URL |
https://sitereports.nabunken.go.jp/112108
|
| DOI 二次元コード |
|
| DOI |
http://doi.org/10.24484/sitereports.112108
|
| 引用表記 |
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2011 『研究紀要』公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
|
|
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2011 『研究紀要』
|
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book|和書|first=和暁|last=川添|first2=健司|last2=宮腰|first3=健|last3=山崎|first4=隆之|last4=大河内|first5=樹|last5=原田|first6=絵美|last6=奥野|first7=浩二|last7=早野|first8=康浩|last8=日吉|first9=邦仁|last9=永井|first10=正明|last10=池本|first11=剛|last11=鬼頭|first12=正貴|last12=鈴木|first13=和彦|last13=伊奈|first14=雅弘|last14=鵜飼|first15=守|last15=宇佐美|first16=誠一|last16=蔭山|first17=真木|last17=武部|title=研究紀要|origdate=2011-03|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| ファイル |
※モバイル対応のPDFは解像度を下げているため、画像が粗く文章が読みにくい場合があります。
|
| 書名 |
研究紀要 |
| 発行(管理)機関 |
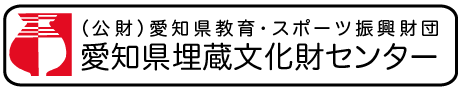 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県
|
| 書名かな |
けんきゅう きよう |
| 副書名 |
|
| 巻次 |
12 |
| シリーズ名 |
|
| シリーズ番号 |
|
| 編著者名 |
|
| 編集機関 |
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
|
| 発行機関 |
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
|
| 発行年月日 |
20110300 |
| 作成機関ID |
|
| 郵便番号 |
4980017 |
| 電話番号 |
0567674163 |
| 住所 |
愛知県弥富市前ケ須町野方802-24 |
| 報告書種別 |
年報・紀要・研究論集・市史研究等・文化財だより
|
| 資料タイプ |
Research Paper |
| 発掘調査報告 |
掲載されていない(発掘調査報告書総目録の掲載対象外) |
| 所蔵大学(NCID) |
|
| JP番号 |
|
| 他の電子リソース |
|
| 備考 |
|
| 所収論文 |
| タイトル |
縄文時代後期注口土器の残存状況に基づく分析 豊田市今朝平遺跡出土資料より |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
川添 和暁
|
| ページ範囲 |
1 - 8
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
縄文
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
土製品(瓦含む)
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
技法・技術
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=和暁|last=川添|contribution=縄文時代後期注口土器の残存状況に基づく分析 豊田市今朝平遺跡出土資料より|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
縄文時代後期の注口土器について、使用・廃棄の痕跡から、その活動行為の復元を論じたものである。今回、部位と残存状況について特に注目して、分析を行った。注口土器自体の分析はもちろんのこと、加えて、注口土器とは歴史的脈略が全くなく、かつ形態的に類似する、中世陶器古瀬戸類の水注との比較・検討を行った。その結果、両者には、残存部位および欠損状況において大きな相違が認められ、注口土器では、注口部を意図的に根元から切断する行為がしばしば行なわれたものと推定した。遺跡から出土する注口土器は、注口部、注口部が除去された胴部、注口部のついたママの完品、胴部片の4群の状態に分けることができ、特に他の破片とは接合しない注口部の存在など、祭祀行為や遺跡間関係を考える上で重要になることを指摘した。 |
| タイトル |
朝日遺跡から出土した石鏃の刺さったシカ腰椎について |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
宮腰 健司
山崎 健
大河内 隆之
原田 幹
|
| ページ範囲 |
9 - 18
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
弥生
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
集落
|
| 遺物(材質分類) |
石器
骨・歯・角製品
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
技法・技術
素材分析
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=健司|last=宮腰|first2=健|last2=山崎|first3=隆之|last3=大河内|first4=幹|last4=原田|contribution=朝日遺跡から出土した石鏃の刺さったシカ腰椎について|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本文で取り上げる石鏃の刺さったシカ腰椎は、朝日遺跡の昭和60 年度調査において出土した遺物であるが、未報告になっていたものである。これまでのX線撮影では、石鏃の形態や陥入状況が不明であったが、奈良文化財研究所のX線CT 撮影によって、それらが明らかになったので報告する。この腰椎は、朝日遺跡の谷Aの左岸(南岸)の貝層内より出土しており、時期は弥生時代中期前半に比定される。部位はニホンジカの第6腰椎にあたり、立位姿勢であれば右斜め前から水平に矢が打ち込まれたと推測され、骨増殖も認められた。石鏃はチャート製の小型の五角形を呈する有茎鏃で、3箇所に衝撃剥離痕がみられる。これらのことから、具体的な狩猟の様子や石鏃の刺突時の状況が判り、骨増殖が認められることにより、本資料の石鏃が弥生時代に行われていたとされる儀礼的な狩猟で使用されたものではなく、狩猟に用いられたものであると推測された。 |
| タイトル |
愛知県一色青海遺跡における昆虫化石を用いた古環境復元 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
奥野 絵美
|
| ページ範囲 |
19 - 24
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
弥生
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
自然物
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=絵美|last=奥野|contribution=愛知県一色青海遺跡における昆虫化石を用いた古環境復元|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本研究では昆虫化石分析の結果をもとに、一色青海遺跡( 愛知県稲沢市) における弥生時代中期の古環境について述べる。一色青海遺跡で弥生時代中期後葉の河道400NR、大溝200SD・600SD から試料を採取し、昆虫化石分析を行った。200SD から得られた合計135 点の昆虫化石群集には、ヒメコガネAnomala rufocuprea やコガネムシMimela splendens など、食葉性のコガネムシ群を中心とした食植性昆虫が多く認められた。この結果から、一色青海遺跡とその周辺に広葉樹を中心とした木本類や、マメ科植物・ブドウなどの果樹からなる植生が広がっていたと推定できる。また、200SD から見つかったコガネムシのAMS14C 年代測定を行ったところ、162calBC-2calAD の値を示した。 |
| タイトル |
石座神社遺跡の遺構と遺物 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
早野 浩二
日吉 康浩
|
| ページ範囲 |
25 - 32
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
弥生
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
集落
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=浩二|last=早野|first2=康浩|last2=日吉|contribution=石座神社遺跡の遺構と遺物|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
豊川中流域に立地する新城市石座神社遺跡は、弥生時代後期・古墳時代前期の集落遺跡である。大型竪穴住居と大型掘立柱建物によって構成される集落の中心施設、検出された320 棟の竪穴住居、破鏡を含む金属製品の出土などから、遺跡は弥生時代後期の拠点集落から古墳時代前期の首長居館への変化の過程を具体的に示す好適な資料と考えられる。 |
| タイトル |
安城市下懸遺跡・惣作遺跡出土の木簡について |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
永井 邦仁
|
| ページ範囲 |
33 - 38
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
古代(細分不明)
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
集落
|
| 遺物(材質分類) |
木製品
|
| 学問種別 |
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=邦仁|last=永井|contribution=安城市下懸遺跡・惣作遺跡出土の木簡について|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
平成20・21 年度の発掘調査で、安城市に所在する下懸遺跡と惣作遺跡からそれぞれ1 点ずつ出土した木簡について報告する。両木簡は奈良時代の可能性が高く、前者が文書木簡で後者が習書木簡と分類される。特に後者については人名「呉部足国」が記されており、西三河地域の古代史に重要な資料を提供したものといえる。 |
| タイトル |
金萩遺跡刻書土器小考 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
池本 正明
|
| ページ範囲 |
39 - 46
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
古代(細分不明)
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
土製品(瓦含む)
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=正明|last=池本|contribution=金萩遺跡刻書土器小考|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本稿では金萩遺跡出土の刻書土器に『』が多い事に注目する。『』は大陸起源の信仰に登場する九字の略号であることが指摘されているが、名古屋市昭和区に所在する八事小堂跡の存在などを評価すると、密教との関わりを想定できる。金萩遺跡資料はいわゆる純密以前の古密教と呼ばれる段階に属する。古密教はその特徴となる現世利益的呪術性を発揮して、猿投窯の製品流通にも宗教的支援を実施していたものと推察でき、金萩遺跡の刻書土器はこうした修法に関連しているものと考えられる。
これは、猿投窯の生産と流通が律令制と関わり深い一面を有していた必然とも言えるであろう。 |
| タイトル |
守山区金屋遺跡について |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
川添 和暁
鬼頭 剛
|
| ページ範囲 |
47 - 54
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
古代(細分不明)
中世(細分不明)
|
| 文化財種別 |
史跡
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=和暁|last=川添|first2=剛|last2=鬼頭|contribution=守山区金屋遺跡について|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本稿では、名古屋市守山区金屋遺跡の資料紹介を行なう。正式な発掘調査は行われていないが、遺跡確認調査の結果、古代・中世の集落跡である可能性を提示した。守山区ではこれまで台地上でしか遺跡の確認ができていなかった。今回、庄内川・矢田川に挟まれた沖積地内の微高地上に立地する本遺跡を確認したことにより、古墳時代以降の地域史研究に新たな考古学的知見を加えることとなった。 |
| タイトル |
小牧山城とその城下町の土師器 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
鈴木 正貴
|
| ページ範囲 |
55 - 62
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
戦国
|
| 文化財種別 |
史跡
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
土製品(瓦含む)
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=正貴|last=鈴木|contribution=小牧山城とその城下町の土師器|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
尾張国を掌握した織田信長は、天下統一を成し遂げるために拠点を清須から小牧、岐阜、安土へと移動した。これらの移転は城下町建設を伴うことが明らかになってきたが、本稿ではその移動の実像の一端を、小牧山城関連の発掘調査で出土した土師器を通して検討した。その結果、土師器生産者は清須から小牧へ移動した可能性が高いが、小牧から岐阜には移動せず一部を除き再び清須に移転したことが推測された。そのあり方は信長の動きとは連動しないことが判明した。 |
| タイトル |
瀬戸市上品野町菩提寺の調査 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
伊奈 和彦
鵜飼 雅弘
宇佐見 守
蔭山 誠一
武部 真木
|
| ページ範囲 |
63 - 74
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
中世(細分不明)
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
社寺
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=和彦|last=伊奈|first2=雅弘|last2=鵜飼|first3=守|last3=宇佐見|first4=誠一|last4=蔭山|first5=真木|last5=武部|contribution=瀬戸市上品野町菩提寺の調査|title=研究紀要|date=2011-03|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/112108|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.112108|volume=12}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本センターでは、平成16、19、20、21 年度と4 次にわたって瀬戸市上品野町にある桑下城跡の発掘調査を行ってきた。桑下城跡の北、直線距離にして300m 程の位置に寂場山菩提寺が存在する。近接して存在する城や窯と寺院とには何らかの関連があるのか。今回我々はこの疑問と興味とから菩提寺について考察することにした。寂場山菩提寺は寺伝によれば天平年間に行基が開いたとされているが、現在は無住の寺となっており、創建当初とはかなり様相を異にしているようである。不明な点の多い菩提寺の近世以前の姿を探るために現地踏査を実施し、文献資料や地元住民からの聞き取りによってさまざまな角度から考察を行った。その結果、文献からは慶長年間以前にこの場に菩提寺ないし観音堂が存在していたことがわかった。また採集遺物では、中世前半期と後半期の2 時期に大別する
ことができ、少なくとも中世後半には何らかの宗教的な施設が存在していたであろうとの推定に至った。 |
|
| 所収遺跡 |
|
| 要約 |
|
関連文化財データ一覧
詳細ページ表示回数 : 1275
ファイルダウンロード数 : 627
外部出力
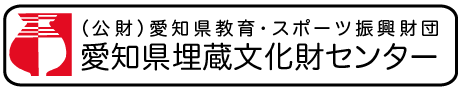 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県
(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県
