研究紀要
| URL |
https://sitereports.nabunken.go.jp/131914
|
| DOI 二次元コード |
|
| DOI |
http://doi.org/10.24484/sitereports.131914
|
| 引用表記 |
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2023 『研究紀要』公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
|
|
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2023 『研究紀要』
|
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book|和書|first=浩二|last=早野|first2=優輝|last2=河嶋|first3=和暁|last3=川添|first4=安信|last4=加藤|first5=有弥|last5=社本|first6=正貴|last6=鈴木|first7=誠一|last7=蔭山|first8=真美子|last8=堀木|first9=峻|last9=渡邉|title=研究紀要|origdate=2023-05-31|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| ファイル |
※モバイル対応のPDFは解像度を下げているため、画像が粗く文章が読みにくい場合があります。
|
| 書名 |
研究紀要 |
| 発行(管理)機関 |
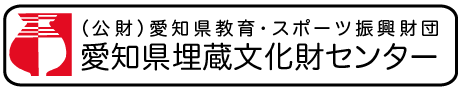 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県
|
| 書名かな |
けんきゅうきよう |
| 副書名 |
|
| 巻次 |
24 |
| シリーズ名 |
|
| シリーズ番号 |
|
| 編著者名 |
|
| 編集機関 |
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
|
| 発行機関 |
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
|
| 発行年月日 |
20230531 |
| 作成機関ID |
|
| 郵便番号 |
4980017 |
| 電話番号 |
0567674163 |
| 住所 |
愛知県弥富市前ケ須町野方802-24 |
| 報告書種別 |
年報・紀要・研究論集・市史研究等・文化財だより
|
| 資料タイプ |
Research Paper |
| 発掘調査報告 |
掲載されていない(発掘調査報告書総目録の掲載対象外) |
| 所蔵大学(NCID) |
|
| JP番号 |
|
| 他の電子リソース |
|
| 備考 |
|
| 所収論文 |
| タイトル |
小折古墳群の研究̶江南市天王山遺跡の家形埴輪̶ |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
早野 浩二
|
| ページ範囲 |
1 - 8
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
古墳
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
古墳
|
| 遺物(材質分類) |
土製品(瓦含む)
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
編年
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=浩二|last=早野|contribution=小折古墳群の研究̶江南市天王山遺跡の家形埴輪̶|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
小折古墳群中の江南市天王山遺跡(「富士塚の西」)においては、尾張型円筒埴輪と形象埴輪が採集されている。その形象埴輪を鰭状装飾(鰭飾り)を表現する家形埴輪として、類例との比較から推定復元案、製作工程案を示し、時期を東山11 号窯式期から東山10 号窯式期と推定した。村絵図、地籍図や空中写真からは、消滅した前方後円墳の存在が想定され、天王山遺跡(古墳)から、江南市曽本二子山古墳、大口町いわき塚古墳に続く有力古墳の系列を把握した。 |
| タイトル |
北設楽郡設楽町 添沢遺跡 出土の鉄鏃について |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
河嶋 優輝
|
| ページ範囲 |
9 - 12
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
中世(細分不明)
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
その他の生産遺跡
|
| 遺物(材質分類) |
金属器
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
年代特定
資料紹介
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=優輝|last=河嶋|contribution=北設楽郡設楽町 添沢遺跡 出土の鉄鏃について|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
北設楽郡設楽町 添沢遺跡では、鉄滓、鞴羽口といった鍛冶関連遺物が自然流路内から出土したほか、同一の流路内から時期不明の鉄鏃1 点も出土しているが、その詳細は未報告であった。
本稿は、観察やX 線写真の検討を通してその形態について推定を行うこと、他の事例との比較検討を通してその位置づけに関して考察を加えることを目的としたものであり、結果として、添沢鉄族は中世初頭のものと位置づけることが妥当であると結論づけた。 |
| タイトル |
愛知県における戦後埋蔵文化財行政草創期の様相について |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
川添 和暁
, 加藤 安信
|
| ページ範囲 |
13 - 22
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
昭和
|
| 文化財種別 |
史跡
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
|
| テーマ |
制度・政治
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=和暁|last=川添|contribution=愛知県における戦後埋蔵文化財行政草創期の様相について|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
愛知県の県指定史跡を一瞥すると、号数についてやや混乱した状況が見える。これは県主体で始動した埋蔵文化財行政当初時の状況を反映したものと考えられるが、別視点から見ると文化財保護法制定後、愛知県としての文化財保護行政を積極的に推進したことを示す証拠として見ることができよう。 |
| タイトル |
岡崎市西牧野遺跡におけるナイフ形石器について |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
社本 有弥
|
| ページ範囲 |
23 - 26
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
旧石器
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
石器
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
技法・技術
編年
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=有弥|last=社本|contribution=岡崎市西牧野遺跡におけるナイフ形石器について|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
岡崎市に所在する西牧野遺跡は県下で有数の旧石器時代の包含層を持つ遺跡である。当センターと愛知県埋蔵文化財調査センターのそれぞれが調査を行い、旧石器時代遺物の出土を多数確認している。
筆者は遺物の垂直分布から上下で石器群が別れる可能性について検討を行った。今回は上層、下層それぞれの石器群からナイフ形石器を抜き出し、その特徴について検討を行う。 |
| タイトル |
岩瀬文庫所蔵「清洲図」について -清須城下町の復元に関連して- |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
鈴木 正貴
|
| ページ範囲 |
27 - 38
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
近世(細分不明)
|
| 文化財種別 |
書籍典籍
歴史資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
城館
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
制度・政治
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=正貴|last=鈴木|contribution=岩瀬文庫所蔵「清洲図」について -清須城下町の復元に関連して-|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
西尾市岩瀬文庫所蔵「清洲図」は岡田啓(康礼)が天保年間末頃に模写した図で、清洲宿を含めた美濃街道を中心に描かれた図に清須城に関連する故地が書き込まれたものである。これについて、近世後期に制作された清洲に関する地誌類や絵図類などと比較・検討した。この結果、清須城に関する故地の調査は『張州府志』を嚆矢とし19 世紀前半に研究が進んだことが判明したが、これらの記述は廃城から200 年以上経過しており、大いに参考になるもののその信憑性にはやや疑問が残るものといえる。 |
| タイトル |
小牧城下町上御園遺跡の鍛冶工房の系譜 -鞴の羽口から- |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
蔭山 誠一
|
| ページ範囲 |
39 - 48
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
古墳
古代(細分不明)
中世(細分不明)
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
その他の生産遺跡
|
| 遺物(材質分類) |
土製品(瓦含む)
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
技法・技術
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=誠一|last=蔭山|contribution=小牧城下町上御園遺跡の鍛冶工房の系譜 -鞴の羽口から-|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
東海地域における古墳時代から近代にかけての遺跡出土の鞴の羽口について素材と形態(羽口送風孔の孔径)から分類し、地域性の抽出と変遷を辿った。また鞴の羽口と一緒に出土する金属製品生産関連遺物の組み合わせと出土した碗型滓など鉄滓の金属学的分析から、小牧城下町上御園遺跡出土の鍛冶工房が美濃地域からの影響を受けたものであることを指摘した。 |
| タイトル |
中狭間遺跡出土赤色顔料の蛍光X線分析 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
堀木 真美子
|
| ページ範囲 |
49 - 52
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
古墳
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
その他
|
| 遺物(材質分類) |
土製品(瓦含む)
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
素材分析
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=真美子|last=堀木|contribution=中狭間遺跡出土赤色顔料の蛍光X線分析|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
安城市中狭間遺跡22A 区から出土した台石および片口鉢に付着する赤色顔料について、蛍光X 線分析を実施した。その結果、台石と片口鉢に付着した赤色顔料より水銀が検出された。 |
| タイトル |
三河地域の縄文時代竪穴建物跡の比較・分析 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
渡邉 峻
|
| ページ範囲 |
53 - 58
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
愛知県
|
| 時代 |
縄文
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
集落
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
建築様式
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=峻|last=渡邉|contribution=三河地域の縄文時代竪穴建物跡の比較・分析|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
設楽ダム関連事業によって新たに発掘された縄文時代竪穴建物跡のデータを加えて、三河地域の縄文時代竪穴建物跡の比較・分析を行い、地域差などの検討を行う。 |
| タイトル |
九州地域の縄文時代貝輪について ̶東海地域からの視点̶ |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
川添 和暁
|
| ページ範囲 |
59 - 76
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
|
| 時代 |
縄文
弥生
|
| 文化財種別 |
考古資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
|
| 遺物(材質分類) |
骨・歯・角製品
その他
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
技法・技術
編年
流通・経済史
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=和暁|last=川添|contribution=九州地域の縄文時代貝輪について ̶東海地域からの視点̶|title=研究紀要|date=2023-05-31|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/131914|location=愛知県弥富市前ケ須町野方802-24|ncid=AA11568230|doi=10.24484/sitereports.131914|volume=24}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
九州地域の縄文時代・弥生時代では、貝輪風習が盛行する。本稿では、縄文時代の貝輪資料に焦点を当て、貝輪群の構造性を把握し、九州地域における縄文時代社会の共通性と地域性を追究する。地域・時期により主体となる貝種が異なることに加えて、ベンケイガイ製とフネガイ科製については独特な加工・装飾を施す事例が出現することを確認した。貝輪は女性との関係性が強い資料であることから、上記を指標とする貝輪群の範囲は、女性側の事情を色濃く示す当時の社会小地域を反映したものと考えられる。また、後期前葉を主体する九州地域から晩期を主体とする吉備地域・東海地域で出現する多数着装事例の出現は、現象の共通性の一方で、着装者の当時の社会的位置について各地域での位置づけが必要であるとした。 |
|
| 所収遺跡 |
|
| 要約 |
|
関連文化財データ一覧
詳細ページ表示回数 : 1671
ファイルダウンロード数 : 1503
外部出力
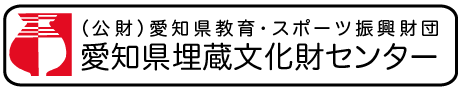 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県
(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
- 愛知県
