大学教育と文化財多言語化
University Education and the Multilingualization of Cultural Heritage
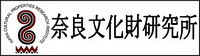 奈良文化財研究所
- 奈良県
奈良文化財研究所
- 奈良県
はじめに
2024年度の春学期、奈良教育大学開講科目「比較言語文化論I」について、 留学生向けの科目としてそのコース内容をさらに充実させるために、新たな3つの目標を掲げた。①奈良の歴史と文化について学ぶこと、②日本の文化政策について理解を深めること、③文化財情報の多言語化に必要な姿勢と考え方を身につけることである。
この授業の一環として、2024年6月12日に国立文化財機構奈良文化財研究所(以下、奈文研)の企画調整部の助力を得て、国営平城宮跡歴史公園にて、奈良の歴史と文化、及びこれらに関わる情報を多言語化する際の注意点などを取り上げた特別レクチャーが開催された。
奈文研は、文化財に関する研究成果を広く発信するため、英語をはじめとした日本語以外の言語での情報提供に力を注いできた。この取り組みは年々強化され、現在では所内に多言語化の専門家が3人在籍している。しかし、理想的な多言語化は一方的な情報発信で完結するものではない。奈文研の多言語化チームは文化財とその多言語化に関する高度な専門知識を備えているが、利用者との接点は十分ではないのが現状である。そのため、今回の連携において、奈文研にとっては国内外の大学生からその多言語化事業に対する率直な意見を聞くことができることが連携の大きな動機となっていた。
また、近年、訪日外国人観光客が急増しており、社会的にインバウンド対応が求められている。この状況により、メディアからもこの話題に関心が寄せられ、本連携事業の一部始終がNHK奈良放送局に取材され、後日、その一部が地域情報番組『ならナビ』で紹介された。[1]
本稿では、この連携事業の内容と意義について述べる。
「比較言語文化論I」について
奈良教育大学は、グローバルな視野を持ちながら、ローカルな文化・歴史・コミュニティーを大切にし、日本全国及び海外から来た学生に対して、奈良の伝統や歴史を紹介する授業やイベントを数多く展開している。
奈良・日本の文化をできるだけ多くの方に理解してもらうためには、その解説方法に工夫が必要である。とりわけ大きな課題は、言語と文化の壁である。この問題に真正面から取り組み、中心課題として取り上げたのが「比較言語文化論I」のコースである。
このコースは、奈良教育大学を取り巻く歴史的・文化的環境について学び、得られた情報を整理し、日本の文化政策に準じた多言語化を実施する構成となっている。多言語化の対象は年度ごとに変わり、それに合わせてコースの内容も大きく変動する。2024年度のコースの流れは以下のとおりである。
まず、受講生は文化財科学と博物館学を専門とする奈良教育大学理科教育講座の教授、青木智史氏に案内され、吉備塚古墳や新薬師寺を中心に奈良教育大学の周辺にある文化財について学んだ。その後、受講生は青木氏のレクチャーに基づいて日本語で情報をまとめた。次いで、異文化の方々に奈良の歴史と文化に興味を持ってもらうためにどのように工夫すべきかを考えながら、情報の発信方法が決定された。具体的には、オーディエンスを国内外の大学生と想定し、彼らの注目を引くために簡単なビデオゲームを作成することになった。続いて、この方針に合わせて文化財情報がセリフ調に書き換えられた。その後、試行錯誤を重ねながら日本語の原稿が作成され、最後にそれぞれの言語に翻訳された。また、並行してゲームに必要なイラストや写真、動画などが作成され、フリー素材の音楽の選定などが進められた。[2]
このコース内容は、文化庁と観光庁が地域の文化財の多言語化事業の理想のあり方として述べているものに限りなく近い、実践的なものとなっている。[3]
当日の流れ
2024年6月12日に、「比較言語文化論I」の一環として、その多国籍(日本、ルーマニア、ドイツ、中国、インドネシア、スペイン、米国)の受講生の中から8人が担当教員である教育連携講座特任講師のYanase Peterとともに、国営平城宮跡歴史公園を訪れた。朱雀門とその周辺の施設(平城宮いざない館など)を訪問した後、奈文研が運営・管理している平城宮跡資料館を見学した。その際、奈文研の展示公開活用研究室主任研究員である小田裕樹が、以前奈文研に所属し資料館の多言語化強化事業に関わっていたYanaseとともに、展示室を案内しながら奈文研の様々な多言語化の取り組みについて解説した。

奈文研の多言語化担当者によるレクチャー後の質疑応答の様子
その後、資料館の講堂にて、企画調整部文化財情報研究室アソシエイトフェローで、多言語化の専門家である楊雅琲(担当言語:中国語)とDudko Anastasiia(担当言語:英語)による、文化財情報の多言語化に関するレクチャーが実施された。そして最後に、多言語化担当者が平城宮跡資料館の多言語化事業に関する第三者評価を得るために、レクチャーに参加した学生に対してアンケート調査を実施した。
続いて、それぞれの多言語化担当者のレクチャーの内容とアンケート調査の結果を紹介する。
中国語担当者の仕事のコツ(中国語担当者のレクチャー)
中国語担当者である楊のレクチャーは、奈文研の多言語化事業の紹介と中国語担当者の翻訳における具体的ワークフローの紹介の二つが主な内容であり、まず以下のように述べた。
奈文研が取り組んでいる文化財の多言語化とは、日本語が理解できない、または得意としない方に対して、奈文研の活動に関する情報や研究成果を伝えることである。具体的に多言語化チームは、研究所の各種データベースやウェブサイト、資料館の題箋などの多言語化を行うほか、各種出版物に含まれる日本語以外の言語での文章の作成や校閲などを主な業務内容としている。
一方、多言語化担当者は日々の実務のかたわら、文化財多言語化そのものの研究も行っている。例えば、国立文化財機構の他の施設の多言語化担当者とベストプラクティスを議論したり、文化財関連用語のシソーラスの開発を進めたりしている。さらに、業務で蓄積されたノウハウと研究成果を『文化財多言語化研究報告』という奈文研刊行のシリーズにおいて、論文や報告の形で発信し続けている。[4]
業務内容はこのように多岐にわたるが、多言語化は一人で行うものではなく、多くの方の助力と蓄積されたノウハウの活用の上で成り立っていることを理解することが重要である。つまり、これまで所内で作成されてきた論考や対訳集、また収集された参考書などを常に手元に置き、参照することがまず大前提である。また、多言語化担当者は所内の研究員の専門知識を借りたり、他の施設の多言語化専門家と意見や情報を交換したり、校閲者などの組織外の協力者とやり取りして日々成長し続けている。このように、多言語化の担当者は多くの方の力を借りながら、日々自分の知識を増やし、スキルを磨くことが欠かせない。
さらに、それぞれの言語には特有の問題が存在している。例えば、奈文研の多言語化事業においては、中国語を繁体字と簡体字の両方で表記する方針を取っている。この二つは一般的に思われているより相違点が遥かに多く、一人で両方を完璧に使いこなしている人は稀である。しかし、奈文研には中国語の担当者が一人しかいない。そうなると、不慣れな表記法でどのように工夫して高品質なテキストを作れるかが課題となる。
このように、一通り多言語化事業の紹介と多言語化の心得の説明が終わった後、学生に、より具体的なイメージを伝えるために、翻訳作業における自身のワークフローを紹介した。
簡単に整理すると、ワークフローは以下のようになる。
1. 日本語の原文に出てきた専門用語を、簡体字と繁体字のそれぞれの参考文献で調べたうえで、それぞれの表記方法での適切な訳語を決定する。
2. 自力で訳語を決められない場合は、専門知識と言語能力を兼ね備えた所内の研究員の意見を求める。
3. 中国語母語話者の理解を助けるための補足情報をテキストに加筆する。
4. それぞれの表記方法の句読点や記号などを整える。
5. 不慣れな表記方法に対して第三者の校閲を依頼する。
この一連の作業では、原文の作者、翻訳者と校閲者の間のコミュニケーションが円滑にできるかどうかが成果物の品質を左右する。とりわけ訳文に補足情報を書き加える際に注意が必要である。
上記を説明した後、過去に作成したいくつかの翻訳の実例を紹介してレクチャーを終えた。
文化財情報の英語化の心得と実践(英語担当者のレクチャー)
英語担当者であるDudkoのレクチャーは、奈文研の英語担当者の仕事内容の紹介が主なテーマであった。まず、研究者向けの報告書の目次や要旨、一般向けのリーフレットやチラシ、来館者向けの資料館の展示パネルや題箋、ネットで配信される動画など、様々な媒体と想定読者によって多言語化の過程と方法が異なると説明した。その後、文化財多言語化という特殊な翻訳作業において、心がけている読みやすい・分かりやすい英訳の基本的なルールについて説明した。それはつまり次のとおりである。
• とりわけ語順と論理的構造に注意し、訳文には英語として不自然な日本語らしい表現を残さないようにする。
• 受動態の乱用を避け、できるだけ能動態を使う。
• 文章の流れやスタイルに配慮しながら、長文を適度に分割する。
• 異なる文化的背景を持つ想定読者のための解説や注釈を過不足にならないよう加筆する。
• 一般向け、研究者向けを問わず、専門用語や難解な語彙、言い回しをできるだけ減らす。
次に、奈文研に英語担当者として着任して間もない頃に依頼された短いパネルの英語化の実例を紹介した。例として取り上げたのは、受講生に馴染みのある唐招提寺の講堂に関する解説パネルのタイトルだけを英語化する依頼であった。このようにタイトルのみを英語化する場合、担当者はタイトルを文字通りに訳さず、パネル全体の内容を精読した上で、どのようにしてたった一文で展示物に関する情報を適切に伝えられるのかを受講生とともに考察した。
レクチャー全体を通じて、多言語化の際に直面する様々な課題とそれらを克服するために必要な手法に焦点が当てられた。締めくくりとして、多言語化業務の将来展望について言及した。すなわち、訪日外国人観光客の増加に伴う多言語化の必要性はもちろんのこと、日本の研究機関の調査・研究結果を国際的な場で発表・公開するためには多言語化が不可欠であると説明し、これから多言語化事業がますます重要になると主張した。
アンケート調査の結果
レクチャーの最後に、平城宮跡資料館の多言語化事業に対する第三者評価を得るため、学生に対するアンケート調査が行われた。アンケートでは様々な意見が寄せられたが、その中から資料館の多言語化においてまだ改善の余地があると指摘されたものをまとめると次のとおりになる。
• 多言語解説の文字のサイズをもっと大きくしてほしい。
• 一部しか翻訳されていないパネルなどの全文を翻訳してほしい。
• 多言語化をもっと充実させてほしい。
• 英・中・韓の表記に三言語が、できるだけ同等に扱われるようにしてほしい。
• 英語が母語ではない人にとっても理解しやすい英語解説になるように工夫してほしい。
多言語化チームはアンケートの結果を展示公開活用研究室と共有し、資料館の展示および多言語化事業の改善に向けた参考資料として活用している。
連携事業の意義と将来
今回の連携事業は、いわゆる「奈良カレッジズ構想」に基づいて実施された。奈良カレッジズ構想とは、奈良教育大学と奈良女子大学の2022年4月における法人統合によって生まれた奈良国立大学機構が、奈良県および関西学術文化研究都市(通称:けいはんな学研都市)などの近隣地域に位置する大学、研究機関、教育機関、企業、自治体などとの連携・協働体制を構築し、それぞれの参画機関の強みと資源の交流による教育研究インフラの強化を図ることで、「高等教育の新たな総合化」を目指すものである。[5]
この枠組みの中で、2024年度から文化財情報の多言語化を大きなトピックとして取り扱う「比較言語文化論I」と長年この課題に取り組み、そのノウハウを文化財担当の専門家の研修や学術雑誌の形で発信してきた奈文研との連携は、自然な流れであったと言えるであろう。特別レクチャーで受講生が現役担当者から直接話を聞くことができ、そこで身につけた姿勢や考え方が、その後の受講生が取り組んだ課題に明らかに現れていた。他方、奈文研は研究所の成果を教育現場へも普及するという役割・目標を果たすとともに、アンケート調査を通じて過去の多言語化事業に対する第三者評価を得た。2025年度以降もこの連携事業の継続が決まっており、さらなる成果が期待されている。
注
[1] 番組の関連セグメントは、以下のURLで閲覧できる。NHK「外国人にもわかりやすい「解説板」作りに取り組む 奈良」(https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20240619/2050016287.html)
[2] ゲームのプログラミングは担当教員が担当し、ゲームエンジンにはストーリーテリングに特化したPython言語ベースのRen’Pyが使用された。
[3] 観光庁「【英語】地域観光資源の多言語解説整備支援事業」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/jirei_shien/tagengo_eng.html)を参照せよ。
[4]『文化財多言語化研究報告』の全巻は『全国遺跡報告総覧』(https://sitereports.nabunken.go.jp/ja)およびその中のオンラインライブラリー(https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/online-library)で閲覧とダウンロードができる。
[5] 詳細は、奈良カレッジズ連携推進センターの公式ウェブサイト(https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/index.html)を参照せよ。
