デジタルアーカイブやインターネット情報を活用した歴史研究事例紹介 ①越谷市指定文化財「野島浄山寺の大鰐口」と本堂火災の関係 ②忍領石分杭の当初位置復元
Introduction of historical research examples using digital archives and other internet information ①The relationship between the Koshigaya City designated cultural property "Owaniguchi of Nojima Josanji Temple" and the fire at the main hall ②Restoration of the original position of the Oshiryo Ishibunkui
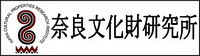 奈良文化財研究所
- 奈良県
奈良文化財研究所
- 奈良県
1.はじめに
越谷市では令和5年8月1日から「越谷市デジタルアーカイブ」を公開した。越谷市デジタルアーカイブがどのような過程を経て市の計画に位置づけられ、計画に基づきどのような手順を踏んでシステムの構築・公開に至ったのか、以前拙稿で紹介した1)。
システム公開後には関連事業として、令和5年8月26日に市民を対象としてデジタルアーカイブ公開記念講演会を実施した(図1)。前半の部は、構築業者による『越谷市デジタルアーカイブでどんなことができるのか?~探す・見る・活用する~』。後半の部は筆者による『「忍領の碑」はどこにあったか?~デジタルアーカイブの活用事例~』である。後半の部の内容はタイトルのとおり、忍領の碑(本稿タイトルの忍領石分杭を指す)が現在地とは異なる場所に存在していたことを、越谷市デジタルアーカイブほかインターネット上の情報を活用して示したものである。
本稿では公開記念講演会での発表内容をベースとして、各機関で公開されているデジタルアーカイブのほか、インターネットで公開されている情報を用いて、本市にまつわる歴史的な事象を論証した事例を紹介する。
具体的には①越谷市指定文化財「野島浄山寺の大鰐口」と本堂火災の関係の提示②忍領石分杭の位置復元、についてである。①については一つの資料(一つのデジタルアーカイブ)がこれまでの疑問を解決した例であり、②については複数の資料(複数のデジタルアーカイブ等)を組み合わせて論証した例である。
なお、本稿の趣旨として、なるべくインターネットから取得できる情報を用いて論を進める。デジタルアーカイブ等が各機関で整備されれば、直接現地に行くことなく一定の成果が出せることを示すことで、各機関においてデジタルアーカイブの整備等が進むことを期待するものである。使用した資料等をインターネットで閲覧する場合は、註のURLを参照されたい。なお各URLのアクセス最終確認日は2025年3月23日である。

図1 越谷市デジタルアーカイブ公開記念講演会チラシ
2.越谷市指定文化財「野島浄山寺の大鰐口」と本堂火災の関係
(1)野島浄山寺とは
越谷市大字野島に所在する浄山寺とは、越谷市教育委員会から平成14 年3月31 日に発行された『越谷風土記』2)によれば、円仁(慈覚大師)創建の天台宗寺院で貞観2年(860)の創立を伝える。寺伝によると円仁が日光に登山して輪王寺を開基したとき、日光山頂より季(すもも)の実を虚空に投げて、この実が落ちて開花した所に一宇の堂を造立することを誓って下山した。それより8年後、円仁は東国巡回の旅に出たが、武州埼玉郡岩槻郷大沼(慈恩寺沼)の脇を通ったとき季の花が見事に咲きほこっていた。円仁はこの季は8年前日光山から空中に投げこんだ、季の実が成育したものと悟り、心願通りこの地に一寺を建立、本尊には自ら彫刻した観世音菩薩像を納めた。これが岩槻の天台宗慈恩寺である。それより同郡野島(越谷市)を通ると、そこにも季が開花していたので、これも自分が投げた季だと悟り一寺を建立、彫刻した延命地蔵の立像を本尊として納めた。これが野島の天台宗慈福寺である。さらに足立郡里村(鳩ヶ谷市)を通ると、そこにも季が開花していたので、ここにも一寺を創立、彫刻した薬師如来像を本尊として納めた。これが里村天台宗慈林寺である。つまりこの三寺とも慈覚大師の慈をとって寺号としている。野島の慈福寺は天文8年(1539)12月に示寂した景春和尚のとき、天台宗より曹洞宗に改められた。したがって景春和尚が当寺の中興開山僧に位置づけられている。二代目は明山長清和尚が継いだが、天正18年(1590)家康関東入国のとき、家康は山林欝蒼としてこの地清浄たりとして、寺号を野島山浄山寺と改めるよう達し、天正19年11月寺領高3石が寄進された。
なお本尊は円仁自ら彫刻した延命地蔵の立像とされる木造地蔵菩薩立像(図2)で、9世紀後半の特徴をもち、平成28年(2016)8月17日に国の重要文化財に指定されている3)。
文化遺産オンラインの解説を転記すると、「越谷市野島の曹洞宗浄山寺の本尊。江戸時代には、数回江戸の湯島天神に出開帳が行われ、その盛況ぶりが、豊国作三枚一組の浮世絵「武州埼玉郡野島地蔵尊於湯島天神境内出開帳図」4)に描かれるなど、「野島の地蔵尊」として広く信仰を集めてきた。近代以降は年2度(2月24日及び8月24日)の縁日以外は秘仏とされ、詳細な調査の機会が得られないまま今日に至ってきた。東日本大震災により破損し、平成24年度に修理が行われたことに伴い、その価値が判明した。」とある。

図2 国指定重要文化財・木造地蔵菩薩立像
(2)越谷市指定文化財「野島浄山寺の大鰐口」とは
越谷市教育委員会から平成10年3月31日に発行された『越谷市の文化財(第12集)』(図3)によれば
天保12年(1841)に奉納された銅製のもので、直径6尺(176cm)、厚さ2尺(60cm)、重量200貫(750kg)という全国でも稀にみる大きさである。この大鰐口の表面には銘が刻まれており、表側にはこの鰐口の奉納者の氏名が80名ほど刻まれている。奉納者をみると、神田紺屋町・本小田原町・日本橋青物町・神田豊島町・馬喰町二丁目・江戸橋四日市・芝金杉浜町・大伝馬町・深川冬木町・千住河原町・二郷半領花和田村・竹塚栗原町・粕壁・高野・大門・菖蒲など広範な地域にわたっている。当時浄山寺では、湯島天神や千住慈眼寺の出開帳、熊谷・深谷・太田などへの巡回出開帳を行っており、人びとの信仰を集めていたが、この鰐口はこうした人びとの浄財によって造られたことが、この奉納者銘から知られる。また裏側には、奉納のいきさつが刻まれており、要約すると以下のとおりである。「この鰐口は、江戸四谷全勝寺二十世全達和尚が国家安穏五穀豊饒を祈って発願したが、不幸中途にて他界したため、 当山二十一世垠宗和尚その発願をみるにしのびず、一般信男信女より浄財を得て、天保12年2月その願望をとげた」5)
大鰐口は図3写真のとおり本堂入口に吊り下げられており、戦時中の金属回収運動の際、天井と釣鐶の間隔が狭かったため、これを撤去できず、あやうく供出を免れた、というエピソードも残されている6)。

図3 越谷市の文化財(第12集)野島浄山寺の大鰐口
(3)野島浄山寺の大鰐口は屋外にあった
さて、浄山寺は文久2年(1862)に本堂が焼失しており、そのためそれ以前の過去帳は現存していない。なお本尊・木造地蔵菩薩立像は火災の際に僧が抱えて持ち出したと伝わっている。
そうした時に、なぜ天保12年(1841)に奉納された「野島浄山寺の大鰐口」は本堂が火災に遭ったにもかかわらず焼失せず、また火災痕跡も無いのか、という疑問がわく。200貫(約750kg)という重量では取り外して屋外に持ち出すことは困難であることは想像に難くない。現にご住職もその疑問を参拝者から問われることがあったそうだが、記録が無いため不明と言わざるを得なかった。
この疑問を明確に答えてくれる資料が「TOKYOアーカイブ」7)で公開されている。「TOKYOアーカイブ」とは「東京都立図書館デジタルアーカイブ」の愛称で、東京都立図書館がデジタル化した、江戸・東京関係資料の画像を検索・閲覧できるデータベースとなっている。
前述のとおり「野島浄山寺の大鰐口」及び「本尊・木造地蔵菩薩立像」は現在の東京都とゆかりがあるため、筆者がTOKYOアーカイブで「野島」と検索したことがきっかけとなり把握できた画像が図4『武州野嶋山之図』8)である。なお、TOKYOアーカイブの画像の多くはパブリックドメインとなっており、本資料もパブリックドメインとなっている。利用者にとっては非常に使いやすいデータベースである。
図4はメタデータによると作者は法橋晃秀、出版年・書写年は嘉永6年(1853)となっており、画像左下の窓内にその情報が確認できる。中央には図5のように大鰐口が茅葺屋根の本堂前面(南側)屋外、覆屋の下に設置され、「武州一のわに口 大サ五尺八寸」と記されている。
つまり時系列としては①天保12年(1841)大鰐口奉納②嘉永6年(1853)図4『武州野嶋山之図』奉納③文久2年(1862)本堂焼失となり、当初は本堂ではなく屋外の覆屋に大鰐口が位置していたため、本堂の火災からは逃れることができた蓋然性が高い、と判明する。これはデジタルアーカイブ上の1つの史料が疑問を解決した事例である。

図4 『武州野嶋山之図』

図5 焼失した本堂と大鰐口
3.越谷市大成町に存在する忍領石分杭の位置復元
(1)忍領石分杭とは
越谷市大成町には「従是東忍領」と刻まれた頂部尖頭型四角柱を呈する石製の傍示杭が1基存在する。図6のとおり、平成16年(2004)秋号広報こしがや季刊版の「歴史を刻む記念碑」という記事において「旧忍藩領の石碑」として紹介されている9)。これは江戸時代の忍領の領域を表示した傍示杭である10)。
本章では、越谷市大成町の傍示杭がもとは現在と異なる場所に存在していたことを古文書に記載されている江戸時代の測量成果と絵図から明らかにすると共に、これまで存在が知られていなかった傍示杭が他にも越谷市大成町周辺に複数存在していたことを新発見の史料から紹介するものである。
なお、傍示杭は埼玉県熊谷市、羽生市、鴻巣市などにも存在し、忍領石標、忍領分石など様々な名称で呼ばれているところであるが11)、これから論考を進めるにあたって用いる越谷市指定有形文化財・古文書『西方村旧記』において、この傍示杭は「忍領石分杭」と呼称されているため、本稿では忍領石分杭と呼称する。

図6 忍領石分杭
(2)忍領東方村と名主中村家
越谷市大成町は市域の南東部に位置し、江戸時代には大成町の一部が武蔵国埼玉郡八條領東方村と呼ばれていた。東方村は元禄11年(1698)に幕府領から忍領に組み入れられ、近隣の見田方、南百、四条、別府、千疋、麦塚、柿ノ木の各村(通称柿ノ木領八か村)と共に廃藩置県まで忍領となっていた12)。東方村は上組と下組に分かれ、両組に名主が置かれたため、名主は2人制であった。
大成町の忍領石分杭は現在、東方村上組の名主を代々勤めた中村家(以下、上組中村家と呼ぶ)の居宅の南西隅付近にある。上組中村家の祖は野与党の一支族である大相模氏のうち、大相模次郎能高(よしたか)と言われている。能高は大相模郷を開発して箕匂(現さいたま市岩槻区)より移住し、大相模氏の祖となった。他に上組中村家の人物として、天明4年(1784)生まれで神道無念流の有道軒と号した中村万五郎がいる。さらに大相模村初代村長の中村重太郎も上組中村家の人である。
なお、東方村下組の名主も代々中村家が勤めている(以下、下組中村家と呼ぶ)。よく混同されるところだが、上組中村家と下組中村家は、別の系譜をもつ家である。
下組中村家は、下組中村家に伝わる系譜によると、祖・中村左近将監は平家千葉氏の庶流である中村太郎・平忠将の遠裔であり、文明年間(1469~1487)に太田道灌に仕え、大相模の郷士となった。その後帰農し、下組中村家は代々村長さ(むらおさ)を勤める家柄として連綿と続いている。現在、下組中村家のかつての居宅は、市指定有形文化財・旧東方村中村家住宅として越谷市レイクタウン九丁目51番地に移築復元し公開されている。
なお、両中村家の位置関係は図10で後述するとおり接しており、位置関係から上組中村家を「西の中村家」、下組中村家を「東の中村家」と呼ぶこともある。下組中村家に遺されていた江戸時代の古文書には「東中村」と記述されているものがあり、江戸時代から混同を避けるように、西・東とも呼び分けられていたことが分かる。
ちなみに両中村家は少なくとも江戸後期には親戚関係となっており、下組中村家第13世中村近義(宝暦2年~寛政6年・1752~1794)は上組中村家中村七郎右衛門政諶の姉りう、と夫婦になっている13)。その他、上組中村家は下組中村家に対して名主の仕事を支援したほか、金銭的な困窮があった際にも援助をしている。まさに両中村家が一体となって東方村の経営に尽力していたことが様々な資料から読み取れる。
若干話が逸れたが、このように由緒ある上組中村家の居宅の一角に忍領石分杭があることから、東方村の中でやや中途半端な位置に存在することは否めないとはいえ、これまで漠然と、筆者も含め多くの方が大成町の忍領石分杭は原位置を保っている、と理解されてきた。
(3)大成町の忍領石分杭の詳細
忍領石分杭についてその詳細を把握するため、越谷市の刊行物(主に市史編さん関係)に忍領石分杭についての記載があるか探したものの、意外にも見つけることができなかった。わずかに先述の平成16年秋号広報こしがや季刊版のほか、平成17年にNPO法人越谷市郷土研究会・加藤幸一の『川のあるまち 越谷文化 第23号』14)のレポートで「旧西方・東方・見田方の村々に散在する石仏石塔の紹介」中「忍領傍示石」と呼称し、スケッチと共に「中村家の南西角地に、領地の境界を標示するために立てられた(中略)傍示石がある。「是より東、忍領」と読む。この石から東は、忍領の飛び地であることを意味し、草加市の柿ノ木村まで続いていた。」と記述されている。
論文としては、管見の限りでは久保康顕らが「調査報告 忍領境界石の現況」の中で越谷市大成町の忍領石分杭の存在に触れたほか15)、澤村怜薫が「忍藩領分杭の成立・建替の経緯と意義」16)で越谷市大成町の忍領石分杭の詳細をまとめている。
澤村論文を参考にすると、銘文は前述のとおり「従是東忍領」であり、寸法は地上高157.5センチメートル、正面巾32.0センチメートル、側面巾23.0センチメートルである。現在地は「越谷市大成町(旧東方村中村家住宅)」と記述されている17)。
以上のように、越谷市大成町の忍領石分杭に限っていえば、これまであまり研究対象として取り上げられたことはなく、わずかにその存在が紹介されることがあった、という程度と思われる。
(4)忍領石分杭の当初位置の復元方法に用いる史料
本章の目的は、忍領石分杭の当初の位置を復元することである。復元に際しては『八潮市史史料編 近世Ⅱ』18)に掲載されている「東方・見田方村絵図」と、越谷市指定文化財・古文書『西方村旧記』を用いる。まず両資料についてその概要を述べる。
1.東方・見田方村絵図
東方・見田方村絵図(図7)は武蔵国埼玉郡八條領西袋村の村役人を代々勤める家柄の小澤家9代目・小澤豊功が描き遺したものである。小澤豊功は天明6年(1786)に生まれ、幼少から江戸へ修学に出ており、林派朱子学の正当を組む儒者で、両国薬研堀に学舎を構える萩原大麓に師事した。豊功26歳の時に八條領見田方村名主宇田氏の女たみと結婚し、六男一女をもうけた。
小澤豊功と東方村との関わりとして、妻の出身である見田方村は東方村の東側に位置し、名主宇田氏は、東方村を含めた通称柿ノ木領八か村を統率する割役名主を代々世襲で勤めた家柄である。
他にも東方村との深いつながりとして、豊功の妹ますは下組中村家第14世中村興治の妻となっており、さらに豊功の三男で文政元年(1818)生まれの千之助は、天保2年(1831)に下組中村家に養子に入り、下組中村家第15世として孫左衛門を襲名している。
さて、『八潮市史史料編 近世Ⅱ』の目次で八條領村々絵図とされている村絵図のうち「十八番の内」と記されている古利根川添の五か村、葛西堀添の八か村、綾瀬川添の四か村、日光道中添の蒲生村などの十八か村の絵図は、天保9年(1838)巡見使が村々を訪ねてきた際に村明細帳に添えて提出されたものの控えである。東方・見田方村絵図は「十八番の内」と記されていないものの、作成年代はこれらと同じ頃の天保期と考えられている19)。
東方・見田方村絵図は絵図の上を北とし、道(往来)を赤線、河川水路を水色、堤を黒線で表記し、寺社を書き入れている。神社は鳥居マークに神社名、寺は切妻風の屋根を表現していると思われるマークに寺名が記される。その他、橋の表現や、河川名、用水名、村名、入会の表記があり、当時の様子が分かる貴重な史料である。

図7 東方・見田方村絵図
2.西方村旧記
西方村とは武蔵国埼玉郡八条領西方村(現越谷市相模町など)のことで、江戸からの行程およそ五里、元荒川に沿った古くからの集落で、もとは大相模郷のなかに含まれていた。西方村は東方村の西隣に位置する。
江戸時代の村高は1540石余、戸数は江戸後期160軒の大村で、村内は五組(寛政五年までは四組)に分かれ、組毎に名主が置かれていた。支配関係は、はじめ高60石の大聖寺領を除きすべてが幕府領であったが、寛文11年(1671)村高のうち173石余が旗本万年佐左衛門の知行地に宛てられた。次いで延宝7年(1679)万年領と大聖寺領を除いた総村高は古河領の飛地に編入されたが、元禄10年(1697)幕府領に復し、以来幕末まで幕領、万年領、大聖寺領の三給所であった。
『西方村旧記』(図8)は、和綴本五冊からなる西方村の事歴を中心とした村史資料の編さん書である。この冊子には表題はないが、各冊子とも青色の厚紙で装丁され、その「地」の部分に「往古ゟ旧記壱」「享保四亥ゟ旧記弐」「明和二酉ゟ旧記参」「寛政六寅ゟ旧記四」「文政元寅ゟ旧記五」と記されている20)。収録文書の下限に文政9年(1826)のものがあるので、おそらく文政9年をそれほど下らない時期に成立したと考えられている。
支配・土地・貢租・水利・交通・鷹場・災害・村況・風俗・寺社・伝記など、あらゆる村方の史料を編年順に編集し、各年代を通じて問題になった事歴を、文書を中心に128項目にまとめて収録したものである。しかも各項目に付記が付され、その前後の経過や沿革を知るための関連史料が収められており、一項目毎に完結史料としてとらえられるようになっているのが本書の特徴である21)。

図8 市指定文化財「西方村旧記」
(5)東方・見田方村絵図の検証
1.東方・見田方村絵図の記載内容
図7のとおり、北には元荒川が描かれており、元荒川左岸には増林村・増森村・中嶋村と書かれている。同じく右岸には麦塚村、南百村、四条村、西方村と書かれている。絵図の名称のとおり、詳細に描かれているのが東方村と見田方村の部分である。
東方村部分(図9)を見ると、本堤の南側に久伊豆、薬王寺、安楽院が描かれ、その東隣に見田方村の牛頭天王、来福寺が描かれる。さらに水路を挟んだ東側には東方村観音寺、さらにその東には浄音寺が描かれる。観音寺と浄音寺の中間地点南側には東方村の玉蔵院があり、玉蔵院沿いの道を南下すると地蔵堂が東側にある。さらにその道を進むと南側以外水路に囲まれた二列の長方形区画に行き当たる。これが東方村の名主を勤めた両中村家の敷地と考えられる。敷地北側には稲荷が、西には桜堂が描かれている。寺社名とその位置、用水・道路などの形状は、現代と十分に対比可能である。
2.四角柱の印
桜堂前の久伊豆神社に突き当たる南北方向の道(なお、この道を境に、西側は西方村である。)と、久伊豆神社から観音寺、浄音寺に至る東西方向の道との交差点部分からやや西にずれた場所に、四角柱もしくは頂部尖頭型四角柱とも見える印が、往来と書かれた右下(南東方向)に描かれている(図9矢印部。矢印は筆者加筆)。
本章ではこの四角柱の印が、上組中村家の敷地内にある忍領石分杭の原位置を示していると仮定し検討を行っていく。
ちなみに、忍領石分杭はかつて木製であったが、大里郡石原村名主の松崎十右衛門が記した御用留(熊谷市指定文化財「浅間山噴火の日記」)の安永9年(1780)正月29日の記事を拠り所とし22)、安永9年に木製から石製へ直されたと考えられている。詳細は澤村論文に詳しいが、東方村の分杭もその頃石製になったと思われる。
前述のとおり、東方・見田方村絵図は天保期(1830~1844)頃の成立と考えられており、絵図が描かれた時期には既に分杭は石製になっていたと考えられる。よって、四角柱の印と現在遺されている忍領石分杭の見た目が酷似していることは、天保期には東方村の分杭も石製となっており、さらに絵図の四角柱の印が忍領石分杭の当初位置を表わしている証左の一つとなるだろう。
3.東方・見田方村絵図と航空写真との対比
次に東方・見田方村絵図と昭和22年の米軍撮影空中写真23)を比較する。図10は東方・見田方村絵図に記載された社寺等を空中写真に落とし込み、さらに上組下組両中村家と(4)-1で触れた宇田家の位置を追記したものである。
絵図に記載されている内容は現在でも遺されているものが多く、両者は良く一致する。両者の位置関係をたどっていくと、四角柱の印はおおむね点線の丸の位置にあたることが分かる。

図9 東方・見田方村絵図詳細(矢印は筆者加筆)

図10 東方・見田方村絵図と昭和22 年撮影空中写真との対比
(6)西方村旧記を用いた検証
1.忍領石分杭に関する記述箇所
本稿では『西方村旧記』のうち「旧記五」24)を取り上げる。「旧記五」の中には「文化十五改元有て文政元寅年
村麁絵図別紙認メ候節往来野道堤土手堀間敷方角分見覚
附村境上手下手中耕地分見ヶ所字名附目録」
という記述がある。これは検見の際の案内や実見の際に都合が良いよう、田畑等の角度や距離を計測し、文政7年(1824)の冬に旧記に書き写したという記述である。
ここには、いろは歌の「い」から「す」の計47、十干の「甲」から「癸」の計10、合わせて57個のルートが書かれており、それぞれ始点となる壱番杭から終点となる留杭までの方向と距離が記されている。ただし、壱番杭から留杭の間には複数の中間地点となる杭(弐番杭・三番杭など)が存在しており、中間地点の杭の数はルートによって様々である。
例えば「戊」のルート(図11)を越谷市デジタルアーカイブの画面を引用しつつ例示すると次のとおりである25)。
戊 利左衛門前ゟ山谷前道江落合迄
壱 午九分 拾三間半
弐 酉七分 拾間
三 午九分 拾五間半
四 申弐分 四間半
五 午九分 拾七間
六 留杭

図11 西方村旧記五 戊ルート該当部分
この例でいうと、壱番杭が利左衛門家の前に存在し、順番に方向と距離を辿っていくと、山谷前道と呼ばれていた道に行きつき、そこに六番杭(留杭)が設置されていたということになる。
さて、本稿で使用するのは「と 蔵後東方村境堤打留杭ゟ忍領石分杭吉川道中央迄」及び「け 不動尊東門前ゟ忍領石分杭迄」のルートである。どちらも「忍領石分杭」が終点(留杭)となっており、始点・中間地点・終点の位置を検討することで、現代の地図に「忍領石分杭」の位置が落とし込めると考えられる。なお、使用する現代の地図は平成23年度作成の越谷市全図である。
ちなみに、前述のとおり『西方村旧記』の成立時期は文政9年(1826)をそれほど下らない時期と考えられている。澤村論文を参考にすると、安永9年(1780)頃東方村の分杭も木製から石製へ直されたと考えられるため、『西方村旧記』で忍領「石」分杭と記述されていることに矛盾はない。
2.西方村旧記における方角の表現方法
検証を進める前に、まず『西方村旧記』では方角がどのように定められているのかを確認する。
旧記記載の方角の表記を例示すると、「卯七分半」、「辰四分二厘」、「卯初五厘」、「辰正中」などがある。語感から何を示しているのか何となく推測されるが、別資料を用いながら少し詳しく見てみよう。
一般的に江戸時代は方角を十二支で表記することが知られている。よって、頭文字は十二支と思われ、『西方村旧記』の当該表記を全て抽出すると、子から亥まで十二支全てが揃っており、むしろ十二支以外の表記(漢字)は確認できない。よって、頭文字は十二支であることが分かり、角度としてはそれぞれ三十度を表わしていると言えるだろう。
十二支に続く文字は「○分」「初」「正中」である。まず「○分」の○には数字が入るが、『西方村旧記』の当該表記を全て抽出すると、壱から九までしか存在しない。このことから、各十二支(三十度)を十等分して表現していることが推測される。現代の分度器は一度毎に目盛りが付されていることが基本であるが、旧記では三度毎の目盛りが基本であるということを示す。
念のため、江戸時代にそのような考え方があったのかを確認するために、ここで村井中漸著 平安天王寺屋市郎兵衛 天明四年(1784)刊『算法童子問』26)を取り上げる。『算法童子問』は首巻・一巻~五巻まで計六巻ある。著者は京都の和算家で、中根彦循の弟子。日常生活に必要な算術を詳細に収録すると共に、コンパスを用いた作図や、独自の測量術について解説を加えている。さらに、末尾には度量衡の全般的な解説も収録している。啓蒙的な算術書ではあるが、西洋から中国まで、題材を幅広く求めている一書である27)。
この本のうち「巻四 海嶋法町見術也 七 分度盤図」(図12)を見ると、十二支の間を十分割しており、『西方村旧記』の表現と一致していることが分かる。
つまり360度を120分割しており、目盛りが一増えるごとに三度増えることになる。前述のとおり『西方村旧記』では「分」の前に入る数字は壱から九までの数字のため、一目盛が三度を表わし、西方村では図12のような測量器具を用いていたことが推測できる。

図12 算法童子問 分度盤図
ただし、『算法童子問』では一目盛りをどのように呼称するのかが記されていない。そこで次に、『規矩要法口伝私録 河原貞頼編 写 九冊』を取り上げる。本書は清水貞徳(1645~1717)が始めた清水流の町見術(測量術)の解説書である。正確に言えば、清水貞徳の著書ではなく、門弟筋の誰かが筆録を整理してできたものがこの写本であり、清水流で使われていた用語の解説が主となっている。
17世紀の間に、幕府は数回にわたって国絵図の作製を全国の大名に命じている。そのために、測量術に対する需要が増え、清水のような測量家がその技術を全国に普及させる契機を得ている。清水流の町見術は、江戸時代を通じて幾つかの支流に分かれていったが、ここで紹介する一連の写本(九冊)は清水貞徳から信濃の河原貞頼(1665~1743)、そして伊勢の村田氏に伝来した内容を収録している。写本の所有者は幕末の和算家・渡辺以親(1795~?)である。
この町見術では、伝承が重なるにつれ、その内容に改善と修正が加えられ、一つ一つの道具に対する解説が詳細になっている。平板測量、規矩元器(方位測定器)による測量の実践の他に、分度の矩(ぶんどのかね)の作図における使い方も説明されている。伊能忠敬が18世紀末の西洋式測量術を導入する以前の段階での、日本的な測量術の一つの到達点を示す資料である28)。
この本の中で、規矩元器の分附をする場合の野帳への記し方が書かれている。それを見ると、図13のごとく、酉と戌の中間では「酉五分」と描かれている。
よって、『算法童子問』と『規矩要法口伝私録』を併せて考えると、十二支の間は十分割され、その一目盛りは○分と呼称することが分かる。つまり一目盛り目は壱分、中間の五目盛り目は五分ということである。

図13 規矩要法口伝私録
次に問題となるのが十二支に続く「正中」「初」の文字であるが、この言葉が不詳である。前述の『規矩要法口伝私録』では、例えば酉の方向を指す場合は「酉支」と表現するようであるが、語感からすると、「正中」は各十二が示す角度幅の中央を指していると考えられる。
続いて「初」も不詳であるが、語感からすると十二支の境目を指すと思われる。
最後に○分半の「半」についても不詳である。現代の感覚で考えれば五厘と同義であるが、旧記には五厘も半も記述があり、また、使い分けもなさそうである。本稿では半=五厘として考える。ただし、半の意味についてはこの推測が間違っていても誤差は三度以下であるため、本稿の主旨には影響がないと考えられる。
以上のことをまとめると、図14のような方向角の表現方法になると考えられる。
具体的に次章から、忍領石分杭を含むルートの検証を進めるが、本稿における角度表記についてのルールを説明する。現在は方向角を表すとき、座標北を零度とし、そこから時計回りに何度であるかを表す。つまりこれまで確認してきた旧記のルールに置き換えると、「子正中」が零度であり、「午正中」が百八十度である。「卯初」は七十五度となる。「午弐分半」は百七十二.五度となる。
なお、厳密に言えば、旧記記載の方角は磁北で表していると考えられるため、座標北と磁北は一致しない。これは地球の極と地磁気の極が一致しないためである。さらに、現在の磁北と江戸時代の磁北にもズレが生じているため(偏角の変化)、もし地図上に旧記記載の方向角を落とし込もうとした場合、磁北に変換すると共に、年代差による偏角の差を補正する必要がある。しかしながら、これからの検証の中で理解いただけると思うが、それらのズレはほぼ無視しても構わないと考えられるため、本稿においては、補正は行わずに論を進めていくことにする。
ちなみに距離は○間と表現されているが、一般的に一間は1.818メートルであることから、本稿でも1.818メートルとし、少数第2位を四捨五入して計算した。

図14 西方村旧記における方向角の表記方法
3.蔵後東方村境堤打留杭ゟ忍領石分杭吉川道中央迄
蔵後東方村境堤打留杭から忍領石分杭吉川道中央迄の方向角と距離について、『西方村旧記』の該当部分を抜き出すと以下のとおりである29)。
と 蔵後東方村境堤打留杭ゟ忍領石分杭吉川道中央迄
壱 午弐分半 四拾間半
此杭囲堤西方東方村境いノ五拾九番打留杭ニ添テ立
弐 酉六分 弐拾弐間半
此杭蔵後畑南角道三方中央ニ立
三 午六分 三拾三間半
此杭墓之角道中央立七郎兵衛屋敷後畑境行
四 辰壱分半 七間半
此杭七郎兵衛表くね添ニ立東江行
五 午七分 弐拾四間半
此杭七郎兵衛屋敷角西方東方境ニ立
六 午六分 六間半
此杭七郎兵衛五郎左衛門屋敷境ニ立
七 酉弐分半 五間半
此杭五郎左衛門屋敷曲り角ニ立
八 未三分 六間
此杭五郎左衛門屋敷内曲り角立
九 午六分半 八間
此杭五郎左衛門仁右衛門屋敷境立
十 午六分半 拾四間半
此杭仁右衛門屋敷内曲り角立
十一 留 杭
此杭忍領石分杭吉川道中央立
壱番杭から十一番杭(留杭)の方向角と距離をまとめたものが表1であり、図化すると図15のようになる。

表1 と 蔵後東方村境堤打留杭ゟ忍領石分杭吉川道中央迄

図15 壱番杭から留杭までの方向角と距離(と)
4.不動尊東門前ゟ忍領分石杭迄
不動尊東門前から忍領石分杭迄の方向角と距離について、『西方村旧記』の該当部分を抜き出すと以下のとおりである30)。
け 不動尊東門前ゟ忍領分石杭迄
壱 卯三分半 四拾間半
此杭不動尊東門前や之弐拾九番ニ添立
弐 卯正中 四拾弐間
此杭吉左衛門畑同人屋敷境立
三 卯正中 弐拾三間半
此杭孫兵衛東光院地境ゟ弐尺先曲り立
四 辰六分 弐拾八間
此杭伝左衛門幸左衛門境立
五 辰初五厘 三拾弐間
此杭惣八長左衛門境立
六 辰正中 拾七間半
此杭長左衛門庄蔵境立
七 辰八分 七間半
此杭庄蔵喜兵衛境立
八 辰初 弐拾五間半
此杭喜兵衛曲立
九 卯九分 三拾七間
此杭孫兵衛畑新左衛門屋敷境四ツ辻道中央立
十 留杭
此杭西方東方境忍領石分杭、と之十一番打留杭落合留ル
壱番杭から十番杭(留杭)の方向角と距離をまとめたものが表2であり、図化すると図16のようになる。

表2 け 不動尊東門前ゟ忍領分石杭迄

図16 壱番杭から留杭までの方向角と距離(け)
5.現代地図との合成
「と 蔵後東方村境堤打留杭ゟ忍領石分杭吉川道中央迄」について、壱番杭は西方村と東方村境の囲堤にあり、いノ五拾九番打留杭に添って立っている、とのことである。囲堤は東方・見田方村絵図の「本堤」と思われ、そのうちの西方村と東方村の境目ということになる。また、三番杭は墓の角道中央に立つ、とある。よって、この位置に相当する場所を想定して現代の図に当てはめると図17「と」ルートのとおりとなる31)。
「け 不動尊東門前ゟ忍領分石杭迄」について、十一番杭(留杭)である忍領石分杭は東方・見田方村絵図の往来に相当する道に行き当たり、吉川道中央に立つ、となっていることから、現代の地図と完全に一致する。
壱番杭は不動尊東門前にあり、やの弐拾九番杭(註:やの弐拾九番杭の説明は「此杭不動尊東門前吉川道三方中央ニ立」と書かれている。)に添って立っている、とのことである。不動尊とは真大山大聖寺のことであり、その東門前が壱番杭となる。東門前を始点に現代地図に当てはめると前掲図17「け」ルートのとおりとなり、現代の東門前から続く道とほぼ一致する。
十番杭(留杭)である忍領石分杭は、と之十一番打留杭の位置と一致するとされている。そのことを裏付けるように、地図に落とし込んだ両者の終点は、ほぼ同じ位置になる32)。
さらに図9と図17を見比べると、東方・見田方村絵図の四角柱の位置と図17でまとめた忍領石分杭の位置が一致することが分かり、東方・見田方村絵図の四角柱(図9で加筆した矢印の先)は忍領石分杭を示していると考えて良いだろう。

図17 西方村旧記記載の測量成果と現代地図の対比
(7)東方村下組中村家に遺された他の忍領石分杭の例
越谷市では、平成29年度に下組中村家の納屋に保管されていた古文書等の資料一式を寄贈いただき、目録の作成が行われている33)。寄贈資料の中には、「従是東忍領」「従是西北忍領」「従是西南忍領」「従是北東忍□」(領カ。以下、本文中では「従是北東忍領」として取り扱う)という4つの資料が存在している。
これは一つの忍領石分杭につき、約24センチメートル×34センチメートルの紙4枚を用いて(裁断した紙を用いる場合がある)、乾拓法により忍領石分杭の文字を写し取ったもので、用紙余白には墨書き又は朱書きで樹立されていた位置と思われる地名が書き込まれている。作成者や作成時期は不明である。4枚の紙を用いて全体を写し取ろうとしているため、紙幅が不足し紙同士が重ならないところもある。史料を合成した画像データは図18のとおりであり、銘文と余白に書かれた地名を表にすると表3のとおりである。

図18 柿ノ木領八か村における忍領石分杭集成

表3 銘文及び添え書き
このうち、「従是東忍領」はこれまで樹立位置の検討を行ってきた忍領石分杭であることは、余白に記された「西方境東方村」の文字や、「従是東忍領」の字体、文字のサイズから明らかである。
このほか、「従是西北忍領」については『草加の金石』34)で紹介されている資料(図19)と一致すると考えられる。『草加の金石』中、当該石分杭はNo.1034とされ、遺物名としては「領地境界石」、所在地は柿木町・宅地内で、角柱型・完形とされており、高さ135センチメートル、幅30センチメートル、厚さ22センチメートルを測り、所在番号は233とされ、『草加の金石』に付属する地図で見ると、詳細な位置は付属地図の縮尺が小さいため不明であるが、柿木のほぼ中央に位置するようである。
「従是西南忍領」と「従是北東忍領」の2点については管見の限りその存在を報告した資料は無い。もし報告されている資料が無く、当該2点の忍領石分杭が滅失しているのならば、下組中村家の拓本資料はその2つの存在を証明する貴重な資料と言える。
さて、図20は忍領の領域を模式的に表わした図である。忍領は飛び地であるため周辺は幕府領等に囲まれている。よって、忍領の領域を表わそうと意図した場合、忍領石分杭は少なくとも四本必要であるため、下組中村家資料はかつて樹立されていた忍領石分杭を写し取ったものと考えられる。なお、図20において、東方村の忍領石分杭はこれまで検討を行ってきた当初の復元位置を、柿木村は『草加の金石』掲載位置を表わし、南百・麦塚は忍領の領域を示すにあたり、このあたりに樹立されるのが自然だと思われる位置を表示したものである。

図19 『草加の金石』報告資料

図20 忍領領域模式図
これまで検討してきた「従是東忍領」例を見ると、西方村からの主要道路沿いに樹立されていたことから、他の忍領石分杭もおそらく主要道路上に建てられていたと考えられる。主要道路から忍領に入った通行者は、これから忍領内に入ると視覚的に認識した上で領内に入ったと思われる。ただし、忍領内に入る道路が複数あることは前述の「八條領村々絵図」のうちの南百村絵図・柿木村絵図・麦塚村絵図を見ても明らかであり35)、忍領内に入る通行者全てが忍領石分杭を認識することは不可能である。よって、忍領石分杭はあくまでもシンボルとしての役割が大きかったと思われ、主要道路以外から領内に入った場合にはこれから忍領内に入る、という認識はできなかったであろう。
澤村氏は忍領石分杭の役割について、「藩権力の権威の誇示にとどまらず、支配領域を顕在化させ(忍藩の風俗統制等の取締向きを)藩領内外の人びとに知らしめる役割をも担った。※()内は筆者加筆」、とする見解を示している。これは他の資料等との関連から導かれた見解であり、卓見に富んでいるだろう。
澤村氏の見解のとおり、忍領石分杭の設置理由は単一ではなく、複合的な理由が存在すると想定されるが、本稿で示したように、忍領石分杭は不動のものとして測量時の目印として間接的にその役割も担っていた。
しかしながら時代の流れは廃藩置県へと向かい、忍藩は消滅することとなったが、道路の拡張や地割の変化等により忍領石分杭が撤去の憂き目にあった際、旧名主等が宅地内などに引き取り、結果、当初とは異なる位置ではあるが、現在に至るまで継承されたと想定される。
(8)まとめ
本章では越谷市大成町(旧東方村)に現存する忍領石分杭について、東方・見田方村絵図に記されている四角柱の印が忍領石分杭の当初位置を表しているのではないかという想定の下、『西方村旧記』に記載されている測量成果と考えあわせることで、東方・見田方村絵図に記されている四角柱の印が忍領石分杭を示していることを復元した。
『西方村旧記』を見ると、村内には様々な杭が配置されており、寺の門前や堀の角など明確な目標から、畑の境目など不明確な目標まで様々多数の杭が配置されていることが読み取れる。これらの杭はおそらく木製であり、不朽や不意の亡失などが発生したことが想定され、その場合は復元する必要が生じる。また、『西方村旧記』では、「い」から「す」、「甲」から「癸」までの五十七のルートが記され、それらは独立したものでは無く、相互に始点・中間地点・終点を共有している。そのような時、忍領石分杭は測量の基準点としての役割を付加され、様々な杭の直接的・間接的な位置関係を担保しており、まさに忍領石分杭が忍領の支配領域を確定(保証)する役割を有していたと考えられる36)。忍領石分杭の設置理由は複数あると考えられ、設置当初の意図かどうかは別にして、本稿では「測量としての基準点」の役割もあったことを示せたのではないだろうか。
最後に、本稿の執筆には栗原利峰、鈴木健弥、戸張真、橋本充史、村田琴音諸氏の協力を得た。また、図7・9の使用にあたっては小澤正直氏、八潮市立資料館の協力を得た。図19の使用にあたっては草加市立歴史民俗資料館の協力を得た。記して感謝申し上げる。
4.おわりに
筆者が学生であった2000年初頭は、インターネットの情報は不確実なものであるという雰囲気があり、それを用いて論文やレポート等を執筆するのは憚られていた風潮があったように思う。現に筆者もその考えに賛同していたし、現在もその考え方が根底にはある。
しかしながら、その後のデジタルアーカイブの普及等により、現在では質の高い一次資料や報告書等がインターネット上で公開されるなど環境が整備されてきている。また、令和元年からのコロナ禍による外出制限では、学生が全国遺跡報告総覧などインターネット上で入手できる情報から調査研究の足がかりをつかむなど37)、今後も資料へのアクセス方法はインターネットを通じたものに比重が置かれることになっていくだろう。
このような状況や越谷市デジタルアーカイブを整備したきっかけもあり、本稿ではなるべくデジタルアーカイブやインターネット情報から得られる情報を用いて論を進めた。考古専攻の筆者としては古文書等の史料を扱うのは門外漢であるため、忍領石分杭や江戸時代の測量方法などについて、先行研究の確認などが不十分な点があるかもしれないが、デジタルアーカイブから得られる情報で一定の成果が出ることが示せたのであれば幸いである。
このようにデジタルアーカイブに関わるあらゆる活動である「デジタルアーカイブ活動」38)を促進させるためには、各機関が保有する情報をインターネット上に公開する、ということが大切になってくるし、その結果、様々な分野におけるデジタルアーカイブの活用が進み、それにより社会における知識の生産と活用の循環が期待される、という事につながるだろう。越谷市デジタルアーカイブもその役割を担うことが出来るよう、今後も内容を充実させていくことが必要である。
【註】
1)莵原雄大「越谷市役所」を対象とした全庁的なデジタルアーカイブの構築2024『デジタル技術による文化財情報の記録と利活用6』 奈良文化財研究所研究報告第41冊
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/online-library/report/19
2)『越谷風土記』は越谷市デジタルアーカイブで画像及びテキストデータを公開している。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/table-of-contents/mp001920-100020/d000260
3)文化庁「文化遺産オンライン」木造地蔵菩薩立像ページ
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/278203
4)武州埼玉郡野島地蔵尊於湯島天神境内出開帳図は
国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能
https://dl.ndl.go.jp/pid/1301469
5)『越谷市の文化財(第12集)』は越谷市デジタルアーカイブで公開している。なお、資料はOCR処理されているため、印刷された文字をテキスト化して取り込むことができる。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/catalog/mp002050-100020
6)『越谷市史二通史下』に記載がある。越谷市デジタルアーカイブで画像及びテキストデータを公開している。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/text-list/d000020/ht004790
7)TOKYOアーカイブトップページ
https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top
8) TOKYOアーカイブ『武州野嶋山之図』ページ
https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000015-00235985
9)越谷市役所2004『平成16年秋号広報こしがや季刊版』
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/koho_pdf/2000/1149_H161015.pdf
10)久保康顕・和泉三奈・押領司綾子・利根川美智子2016「調査報告 忍領境界石の現況」『行田市郷土博物館研究報告 第8集』 また、本稿では忍藩の領域を「忍領」と呼称する。
11)澤村怜薫2021「忍藩領分杭の成立・建替の経緯と意義」『埼玉地方史 第81号』では、呼称について、忍領石標、忍領分石、境界標柱、忍領境界碑、忍領境界石など様々あることを紹介し、澤村論文では、石製傍示杭の建立主である阿部家の郡方日記の書抜に「御領分御分杭」と記載されていることに準拠して「忍藩領分杭」と呼称することで論を進めている。
12)越谷市ホームページ「越谷市指定有形文化財 旧東方村中村家住宅」https://www.city.koshigaya.saitama.jp/toiawase/shisetsu/dentobunka/kyuuhigasikatamuranakamurake.html
13)越谷市教育委員会2015『旧東方村中村家住宅展示解説図録』11ページに記載がある。越谷市デジタルアーカイブで公開している。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/viewer/mp002040-100020/2022-100010-019/
14)書誌情報の詳細は越谷市立図書館ホームページのとおり
15)註10)前掲久保ほか論文。
16)註11)前掲澤村論文。
17)現在地については、もし、澤村論文の旧東方村中村家住宅が市指定文化財としての名称を指しているのであれば、これは誤りである。前述のとおり指定名称である旧東方村中村家住宅は下組中村家を指すが、忍領石分杭の現在地は上組中村家の居宅内である。よって、上組下組両中村家を混同していることになる。一方、旧東方村の中村家住宅という意味として記述しているのであれば間違いではないが、上組中村家と下組中村家のどちらを指すか不明となってしまう。よって、澤村論文について正確を期すのであれば、現在地は「旧東方村上組中村家住宅」とした方が良いと思われる。これにより澤村論文の内容が損なわれるわけではないが、混同されることがままあるので、ここで指摘しておく。
18)八潮市役所1987『八潮市史史料編 近世Ⅱ』
国立国会図書館デジタルコレクションにおける図書館・個人送信サービスで閲覧可能
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001848084
19)図7東方・見田方村絵図の使用にあたっては埼玉県八潮市立資料館において利用申請を行い、高精細画像の提供を受けている。
20)図8ほか西方村旧記の外観画像は越谷市デジタルアーカイブで公開している。
21)『越谷市史続史料編一』に記載がある。越谷市デジタルアーカイブでテキストデータを公開している。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/text-list/d000030/ht000040
22)註11)前掲澤村論文。
23)国土地理院ウェブサイト地図・空中写真閲覧サービス(整理番号USA・コース番号R393・写真番号126・撮影年月日1947/10/23(昭22))
https://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=216343&isDetail=true
24)『旧記五』は越谷市デジタルアーカイブで画像・テキストデータと共に画像と翻刻の重ね合わせビューアーで公開している。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/catalog/mp000050-100040
25)越谷市デジタルアーカイブ上の該当部分は139ページ目である。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/viewer/mp000050-100040/2022-100040-005/
26)国立国会図書館デジタルコレクション『算法童子問 首1巻5巻』
https://dl.ndl.go.jp/pid/3514942/1/1
27)国立国会図書館ウェブサイト「江戸の数学>第2部 国立国会図書館の和算コレクション>和算資料ライブラリー> 3和算の展開>和算家たち>7 算法童子問 首1巻5巻
村井中漸著 平安 天王寺屋市郎兵衛 天明4(1784)刊 合1冊 <202-229>」https://www.ndl.go.jp/math/s2/3.html
28)国立国会図書館ウェブサイト「江戸の数学>第2部 国立国会図書館の和算コレクション>和算資料ライブラリー > 4実学・測量関係>測量術>清水流町見術>4 規矩元法別伝 清水貞徳述 石田景如記 写 1冊 <140-201>」
https://www.ndl.go.jp/math/s2/4.html
29)越谷市デジタルアーカイブ上の該当部分は99ページ目である。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/viewer/mp000050-100040/2022-100040-005/
30)越谷市デジタルアーカイブ上の該当部分は120ページ目である。
https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/viewer/mp000050-100040/2022-100040-005/
31)相模町(かつての西方村)と大成町(かつての東方村)の境目は現在でも一直線ではなく、格子目西端境目で表記したように複数回のクランク状になる。これは当時の地境を表現していた名残が現代でも引き継がれていることを表わしていると同時に、当時の測量が正確であること、前述した方向角の前提や座標北と磁北のズレが本稿で扱う図面縮尺においては特に考慮する必要が無いことを示している。
32)厳密に図17を見ると、終点の位置には若干のズレが生じている。「と」が現代の地図と完全に一致している現状では、方向角と磁北のズレを補正しないことによる誤差の影響は低いと考えられる。なぜズレているかを考えた時、当時の測量方法の誤差が考えられる。『西方村旧記』の中で測量方法は記載されておらず、登戸村関根氏の主人が加勢のため差し越してきたという事が分かるのみである。おそらく当時測量した際には、壱番杭から弐番杭の方向角と距離を測り、次に弐番杭から三番杭の方向角と距離を測り、というように順番に測量したと考えられる。ただし、このような方法、つまり現代でいうところの開放トラバース測量だと誤差が累積してしまう。現代の道路とズレが大きい「け」を見た時、四番杭の方向角が百二十三度ではなく百二十一度であった場合、留杭は「と」の留杭とズレることなく、ほぼ一致する。よって、どこかの杭もしくは複数の杭において方向角の測量誤差があったと思われる。
33)目録は越谷市デジタルアーカイブで公開できるよう準備を進めている。
34)草加市1984『草加市史調査報告書 第二集 草加の金石』
国立国会図書館デジタルコレクションにおける図書館・個人送信サービスで閲覧可能
https://dl.ndl.go.jp/pid/12205917
35)註18)前掲資料を参照願いたい。
36)前述のとおり西方村は忍領ではないが、忍領との境を示すことは間接的に忍領の領域を示すことになる。なお、管見の限り東方村の記録に測量関連史料は見いだせていない。
37)高田祐一ほか2023「学生座談会「コロナ禍は、学生の文献収集活動にどう影響を与えたか?次世代の調査研究環境のあり方を考える」」『デジタル技術による文化財情報の記録と利活用5』奈良文化財研究所研究報告 第37冊
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/120107
38)「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドライン
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/dai16/siryou1-1.pdf
