第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会
| URL |
https://sitereports.nabunken.go.jp/141914
|
| DOI 二次元コード |
|
| DOI |
http://doi.org/10.24484/sitereports.141914
|
| 引用表記 |
歴史公園鞠智城・温故創生館 2025 『鞠智城跡「特別研究」発表要旨集13:第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会』熊本県教育委員会
|
|
歴史公園鞠智城・温故創生館 2025 『第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会』鞠智城跡「特別研究」発表要旨集13
|
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book|和書|first=|last=歴史公園鞠智城・温故創生館|title=第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会|origdate=2025-03-09|date=2025-03-09|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/141914|location=熊本市中央区水前寺6丁目18番1号|doi=10.24484/sitereports.141914|series=鞠智城跡「特別研究」発表要旨集|volume=13}}
閉じる
|
| ファイル |
※モバイル対応のPDFは解像度を下げているため、画像が粗く文章が読みにくい場合があります。
|
| 書名 |
第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会 |
| 発行(管理)機関 |
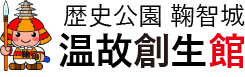 歴史公園鞠智城・温故創生館
- 熊本県 歴史公園鞠智城・温故創生館
- 熊本県
|
| 有償頒布・配布ページ |
http://www.kumamoto-bunho.jp/index.html
※ 有償頒布・配布していない場合もあります |
| 書名かな |
だい13かいきくちじょうあととくべつけんきゅうせいかほうこくかい |
| 副書名 |
発表レジュメ集 |
| 巻次 |
|
| シリーズ名 |
鞠智城跡「特別研究」発表要旨集 |
| シリーズ番号 |
13 |
| 編著者名 |
|
| 編集機関 |
歴史公園鞠智城・温故創生館
|
| 発行機関 |
熊本県教育委員会
|
| 発行年月日 |
20250309 |
| 作成機関ID |
43000 |
| 郵便番号 |
8628609 |
| 電話番号 |
0963831111 |
| 住所 |
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
| 報告書種別 |
配布資料(現地説明会・展示解説・発表要旨)・講演会資料集・ガイドブック
|
| 資料タイプ |
Research Paper |
| 発掘調査報告 |
掲載されていない(発掘調査報告書総目録の掲載対象外) |
| 所蔵大学(NCID) |
|
| JP番号 |
|
| 他の電子リソース |
|
| 備考 |
|
| 所収論文 |
| タイトル |
城柵との比較からみた鞠智城の管理・経営体制 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
岡﨑 怜央
, Okazaki Reo
|
| ページ範囲 |
1 - 7
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
岩手県
宮城県
福岡県
熊本県
鹿児島県
|
| 時代 |
飛鳥白鳳
奈良
平安
|
| 文化財種別 |
史跡
書籍典籍
歴史資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
城館
交通
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
文献史学
|
| テーマ |
制度・政治
流通・経済史
軍事
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=怜央|last=岡﨑|contribution=城柵との比較からみた鞠智城の管理・経営体制|title=第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会|date=2025-03-09|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/141914|location=熊本市中央区水前寺6丁目18番1号|doi=10.24484/sitereports.141914|series=鞠智城跡「特別研究」発表要旨集|volume=13}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本稿は鞠智城と東北の城柵について、管理・経営体制の面から両者を比較することで、9 世紀における鞠智城の機能とその地域的な役割を明らかにすることを目的とする。
城柵は蝦夷支配の拠点として、補給が不安定な地域において蝦夷支配を展開することが想定された組織であった。その管理・経営体制においては、付属民である柵戸や夷俘が現地での人的・物的資源の生産・供給を担うことで、自律的な組織として機能した。また、この管理・経営体制を維持するため、城柵と柵戸・夷俘との間には、有事における相互協力の関係が成立していたことを確認した。
これに対し鞠智城は、大宰府の指揮下で対外防衛の機能を果たすことを目的としていたため、城柵のような自律性を発揮する必要がなく、実際にそのような管理・経営体制も構築されていなかったことを明らかにした。
次に、鞠智城の管理・経営体制に変化が生じる時期として、弘仁4 年(813) の大宰府管内での軍団兵士制の縮小に注目した。そして、考古学的な成果を踏まえつつ、これ以降の鞠智城では、周辺住民が城の管理・経営に必要な経営基盤として組み込まれ、経営に必要な人的・物的資源の生産・供給を担うようになったことを明らかにした。またこれによって鞠智城は、城柵と同様、自律的な組織へと再編成されたとみられることを明らかにした。
最後に、鞠智城が自律的な組織として再編成された背景として、当時の新羅に対する警戒感があったことを示した。また、この頃の鞠智城に不動穀が貯蓄されていた事実から、鞠智城が対新羅用の拠点として機能するとともに、かつ逃げ込み城としての機能を有していたとし、鞠智城と周辺住民との間には、城柵で見られたような相互協力の関係が成立していたと結論付けた。 |
| タイトル |
地域支配における古代山城の役割 |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
柿沼 亮介
, Kakinuma Ryousuke
|
| ページ範囲 |
8 - 15
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
大阪府
岡山県
広島県
山口県
香川県
愛媛県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
|
| 時代 |
飛鳥白鳳
奈良
平安
|
| 文化財種別 |
史跡
書籍典籍
歴史資料
|
| 史跡・遺跡種別 |
城館
|
| 遺物(材質分類) |
|
| 学問種別 |
文献史学
|
| テーマ |
制度・政治
軍事
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=亮介|last=柿沼|contribution=地域支配における古代山城の役割|title=第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会|date=2025-03-09|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/141914|location=熊本市中央区水前寺6丁目18番1号|doi=10.24484/sitereports.141914|series=鞠智城跡「特別研究」発表要旨集|volume=13}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本研究では古代山城について、その築造・修築・廃絶などの過程をおいながら、時期ごとの国際情勢や国内支配の様相と関連して山城がどのように整備され、また地域支配においてどのような役割を果たしたかを検討した。
『日本書紀』における古代山城の築城記事からは、長門国の城・大野城・基肄城と、高安城・屋嶋城・金田城という二段階で山城が整備されたことが窺える。古代国家は第一段階として、筑紫と関門海峡をまずは死守すべき防衛ラインとして位置づけて山城の運用を開始した。続く第二段階として築かれた高安城は最終防衛ラインであり、かつ飛鳥・藤原の宮都と大阪平野を結ぶ畿内の中央部に位置することから、政権の基盤たる畿内を支配する上での役割をも担っていた。屋嶋城は瀬戸内海への侵攻に備えたものであるが、同時期の瀬戸内地域では交通路や地域支配の拠点から近いところに「一般の軍事拠点」としての山城も整備され、それらは一体として運用された。しかし、あくまで各地で一般的にみられる現象のため、史書には記録されていない。一方で屋嶋城は、想定侵攻経路の監視に特化した特殊な山城であることから、史書にも名がみえると考えられる。金田城は敵襲の監視とそれを筑紫に伝達する役割を担い、堅固な石塁には「見せる城」として意味があったが、島嶼の領域的防衛は想定されておらず、軍事的緊張の緩和にともなっていち早く廃絶した。
多くの古代山城は8 世紀初頭まで存続したが、唐と新羅の対立によって670 年代には日本列島侵攻の可能性は低下していた。それでも存続した理由としては、高句麗の残存勢力や耽羅からの外交使節の来日がなくなる中で、「中華」としての自国の体裁を維持すべく、古代国家が南西諸島や隼人などへの支配を強化したことが関係している。そのため各地の山城は大宰総領の下で維持され、特に南部九州における「辺境」支配の後背地として重視された大野城・基肄城・鞠智城は「繕治」された。
大宝律令の下で山城の管理は大宰総領から国司に移管されたが、引き続き大宰府がおかれた西海道を除く地域では山城は衰退していった。大宝律令の編纂時点では「城」制度の構築が目指されていたが、養老律令の段階で山城の維持は放棄された。一方で西海道の山城は、その軍事的側面は国司の管轄下で、城内に設置された倉庫の管理は大宰府によって担われる形で存続した。倉庫に収められた物資が西海道諸国の共用物となったことにより、日本列島と朝鮮半島との間の海域の人々の活動が活発化すると、たとえそれが肥後国の管内で起こったことではなかったとしても鞠智城まで影響が及び、怪異記事という形で史書に記録されることになった。 |
| タイトル |
倭政権の国境域防衛機構 -軍事的施策と宗教的施策- |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
小嶋 篤
, Kojima Atushi
|
| ページ範囲 |
16 - 22
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
福岡県
熊本県
|
| 時代 |
古墳
飛鳥白鳳
|
| 文化財種別 |
史跡
書籍典籍
歴史資料
考古資料
埋蔵文化財
|
| 史跡・遺跡種別 |
官衙
城館
交通
古墳
祭祀
|
| 遺物(材質分類) |
土器
金属器
|
| 学問種別 |
考古学
文献史学
|
| テーマ |
制度・政治
宗教
軍事
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=篤|last=小嶋|contribution=倭政権の国境域防衛機構 -軍事的施策と宗教的施策-|title=第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会|date=2025-03-09|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/141914|location=熊本市中央区水前寺6丁目18番1号|doi=10.24484/sitereports.141914|series=鞠智城跡「特別研究」発表要旨集|volume=13}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
本研究では、倭政権の軍事的施策と宗教的施策を検討し、国境域防衛機構の全体像描写を試みた。軍事的施策の一つとして施行された古代山城の築城は、古墳時代後期より整備されてきた戦時侵攻体制( 軍事動員・物資備蓄) 上に存在しており、交通路や拠点的ミヤケの分布とも一定の相関関係をもつ。外敵襲来時の「戦場」となる筑紫洲北部では、『日本書紀』では古代山城築城記事に先んじて、防人・烽配備とともに水城築造が記載されるため、筑紫洲を縦走する南北路の閉塞が重要視されていることが分かる。次いで築城記事がある大野城と、その対面にある小水城群・牛頸丘陵は、水城を挟んで鶴翼状配置を採り、水城前面での外敵迎撃が基本戦略であったと把握できる。この主要迎撃地点で臨戦態勢を採っていたのが筑紫大宰である。筑紫大宰が動員する公的軍隊は、任地の筑紫国造軍が主力であり、同国造軍は鞠智城とも接続する南北路を利用して外征軍動員を重ねてきた実績がある。つまり、水城前面での外敵迎撃は戦術的優位だけでなく、軍事動員・兵站確保という戦略的優位も確保していたと評価できる。
一方で、外敵襲来が警戒される玄界灘航路の要衝・宗像地域は、古代山城分布の空白地である。宗像地域は古墳時代(四世紀)より倭政権が信仰してきた宗像神の坐す地であり、同地には充神民が居住してきた。古代山城築城期と重なる飛鳥時代後半(七世紀後半)までには神郡が宗像神に奉じられ、倭政権の宗教的施策として重要視されていたことが分かる。宗像郡郡司・宗像神社神主を同族のみで独占する宗像君(宗形朝臣氏)と、その服属集団である宗像部は玄界灘航路沿いの港湾に分布し、古墳時代中期以後、筑紫君とならぶ大規模動員力を古代山城築城期にも保持していた。つまり、宗像神が坐す神郡は、軍事と宗教の両面で守護された土地であったと評価できる。
総括すると、「戦場」となる筑紫での古代山城配置には、地質環境や交通路といった即物的な軍事目的だけでなく、①各国造軍を率いる氏族の歴史的実績や、②倭政権の国家的宗教体系も反映していると結論できる。 |
| タイトル |
古代山城成立地における考古学的地域史研究 ―おつぼ山神籠石をケーススタディーとして― |
| 英語タイトル |
|
| 著者 |
徳富 孔一
, Tokudomi Kouiti
|
| ページ範囲 |
23 - 30
|
| NAID |
|
| 都道府県 |
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
|
| 時代 |
弥生
古墳
飛鳥白鳳
|
| 文化財種別 |
史跡
考古資料
埋蔵文化財
|
| 史跡・遺跡種別 |
集落
城館
その他の生産遺跡
墓
古墳
|
| 遺物(材質分類) |
土器
金属器
|
| 学問種別 |
考古学
|
| テーマ |
制度・政治
流通・経済史
軍事
|
| 他の電子リソース |
|
| 引用表記 |
wikipedia 出典テンプレート :
{{Citation|first=孔一|last=徳富|contribution=古代山城成立地における考古学的地域史研究 ―おつぼ山神籠石をケーススタディーとして―|title=第13回鞠智城跡「特別研究」成果報告会|date=2025-03-09|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/141914|location=熊本市中央区水前寺6丁目18番1号|doi=10.24484/sitereports.141914|series=鞠智城跡「特別研究」発表要旨集|volume=13}}
閉じる
|
| 抄録(内容要約) |
佐賀県武雄市橘町に所在するおつぼ山神籠石は、杵島山山塊西麓部に位置し、有明海の入江状地もしくは接続河口部を直視することは可能だが、有明海の海原を直視することは出来ない。従って、おつぼ山神籠石には、対有明海防備ではない役割・性格が考えられる。そこで、本稿では、おつぼ山神籠石が成立する六角川中流域及び武雄盆地における弥生時代早期から古墳時代終末期(飛鳥時代)までの考古学的地域史研究をミクロ的に行い、その上で、マクロ的に六角川中流域の地域的特性を考察する。
まずミクロ的な地域史研究では、武雄川流域北岸と六角川中流域が、基本的に弥生時代早期以来、遺跡形成を継続させる地域であるが、武雄川流域北岸が古墳時代前期前葉以降に空隙を生むのに対し、六角川中流域は遺跡形成が鈍くなりながらも継続させ、古墳時代中期後葉以降に首長墓系譜を確立する地域となることが分かる。そして、弥生時代後期に中広形銅矛が埋納された玉江遺跡は、そこより六角川上流に遺跡展開を見ないことから、フロンティアな遺跡であり、弥生時代終末期以降に遺跡形成が進み、古墳時代には竪穴建物と掘立柱建物が並ぶ景観となる。また、陸路で接する藤津郡域の杵島山山塊西南部では古墳が確認されないことや、杵島山山塊北部では別の首長墓系譜が成立していることからも、六角川中流域はフロンティアな性格を有した小世界を築いていたと言える。
次にマクロ的な考察では、六角川中流域は、弥生時代において環濠集落や金属器といった玄界灘沿岸文化と台付甕や肥前型器台といった環有明海的文化の十字路であり、それが古墳時代前期前葉以降の斉一的な古墳文化(布留式土器様式・前方後円墳)によって一端解消されたにせよ、古墳時代中期後葉から筑紫君の関与の下で再びフロンティアな場所として機能したことが分かる。
それらのことから、六角川中流域に成立する有明海準直視型古代山城のおつぼ山神籠石は、辺境警備の役割・性格を有し、大宰府防衛における南面の防備として、筑紫君の版図ないし版図外に睨みを利かせていたことが考えられる。 |
|
| 所収遺跡 |
| 遺跡名 |
鞠智城跡 |
| 遺跡名かな |
きくちじょうあと |
| 本内順位 |
|
| 遺跡所在地 |
熊本県山鹿市菊鹿町米原ほか |
| 所在地ふりがな |
くまもとけんやまがしきくかまちよなばる |
| 市町村コード |
43208 |
| 遺跡番号 |
100 |
| 北緯(日本測地系)度分秒 |
|
| 東経(日本測地系)度分秒 |
|
| 北緯(世界測地系)度分秒 |
330010 |
| 東経(世界測地系)度分秒 |
1304700 |
| 経緯度(世界測地系)10進数(自動生成) |
33.002777 130.783333
|
※当該位置周辺を表示し、同一名称の遺跡データが存在する場合は遺跡をポイント表示します。
|
| 調査期間 |
|
| 調査面積(㎡) |
|
| 調査原因 |
|
| 遺跡概要 |
| 種別 |
城館
|
| 時代 |
飛鳥白鳳
奈良
平安
|
| 主な遺構 |
掘立柱建物跡
礎石建物跡
貯水池跡
土塁跡
城門跡
|
| 主な遺物 |
土師器
須恵器
瓦
墨書土器
木製品
木簡
仏像
|
| 特記事項 |
古代山城
「秦人忍□五斗」木簡
銅造菩薩立像 |
|
|
| 要約 |
|
関連文化財データ一覧
詳細ページ表示回数 : 32
ファイルダウンロード数 : 35
外部出力
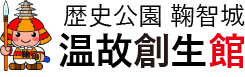 歴史公園鞠智城・温故創生館
- 熊本県
歴史公園鞠智城・温故創生館
- 熊本県
